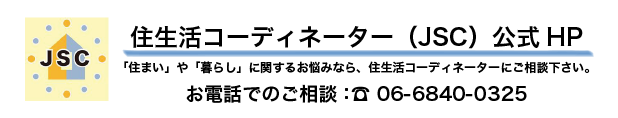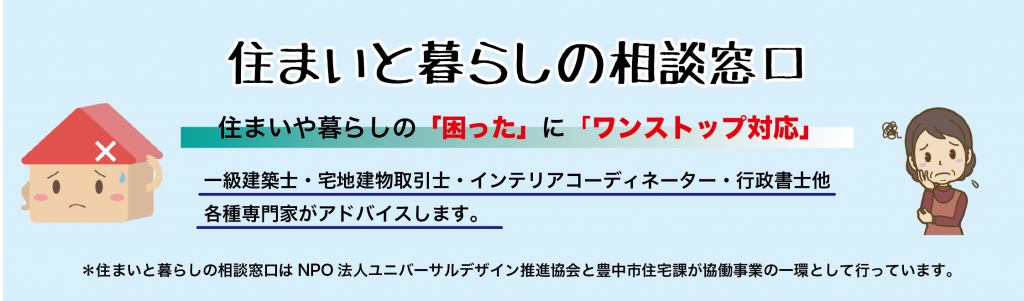家の中は安全で快適な空間になっていますか?
家の中は安全で快適な空間になっていますか?
「モノがいっぱいでそろそろ片づけないと」と思っていても、日々の生活に追われてなかなか取りかかれないと感じている方は多いのではないでしょうか?
長年住み慣れたわが家も、モノのせいで掃除がしにくい、住みにくい場所になっていたら快適とは言えませんね。
実は、高齢者にとって家庭内事故の発生率は高く、事故発生場所に注目してみると、1位「居室」、2位「キッチン・ダイニング」、3位「階段」となっています。
片づけがうまくできていないと、思いもよらない転び方でけがをするなど、家の中が危険な場所になってしまうのです。
転倒などの家庭内事故を防ぐために、「片づけ」は大至急取り組みたい問題です。
こんな問題ありませんか?

モノを整理して、「今」生活に必要なモノを、自分も家族も使いやすく収納すると、、、、、
こんないい変化が起こります

片づけを成功させるためのポイント!

片づけを効果的に進めるために
「さぁ、片づけるぞ!」と思い立って何から取り掛かりますか?
効果的に進めるためには、 整理 → 整頓 → 収納 → 掃除 の順番で進めることが大事です。
まず整理の部分で、使うモノ をしっかり選びだすことが大事なポイントです。この写真は一人暮らしの方の女性の整理前と整理後の鍋の様子。
しっかりと 使う鍋&ざる を選び、適切な場所に収納すると、こんなにゆとりの空間が生まれ、取り出しやすくしまいやすい収納が実現できます。

整理の部分で、使うもの が選び出せれば、片づけの8割は成功した!といえるくらい大事な部分なのです。

整理の手順
1 全部出す
決めた範囲のモノを全部出して把握します。
例)キッチンの食器棚の食器を全部取り出してみます。

取り出す過程で、「こんなお皿を持っていたんだ!」とか「ここにしまっていたのね」なんて自分の持ち物なのに発見があるかもしれません。
”全部出し”をしてすべてを見ることが目的です。
2 分ける
まず大きなグループで種類ごとに分けます。
例)3つのみを例としてあげました。

何がいくつくらいあるのか分けるとわかります。
その後、小さなグループで再び分けます。
例)皿のグループを3つ(大皿、中皿、小皿)に分けています。

3 減らす
大皿、中皿、小皿それぞれのグループで、どんな場面で使うのか、そしてどの皿が何枚必要か?と考えながら使う食器のみを選びだします。
そこで残ったものは、「今」何らかの理由があって使わないと判断できれば処分(捨てる・ゆずる)することになるでしょう。
4 収納する
片づけの最終段階です。
残った食器を、使うときにどこにあれば使いやすいのか、どれくらいの頻度で使用するのか、を考えながら場所決めし、収めます。
よく使うお皿と一年に数回しか出番のないお皿とでは、しまっておく位置も違うと思います。
<取り出しやすく><しまいやすい>を意識して、収納場所の70−80%の量までに収めるのが良いでしょう。
以上基本の手順でした。
ポイントは「分ける」です。
途中であきらめないで、しっかり分けることができれば、使いやすい食器棚に変化していくこと間違いなし、です。
シニア世代の暮らしに備えて

〜家の中を暮らしやすく整えて、安全で快適な生活を実現しましょう〜
セミナー活動
整理収納アドバイザー資格を持つJSCメンバーにて、暮らしの中で実践できる整理術をお伝えするセミナーも行なっています。